Last updated on 2025-10-26
シグマ製コンパクトデジタルカメラ・SIGMA DP1、DP1s、DP1x のレビューと写真作例
- 本サイト表示の広告詳細は本リンク先に記載、本文中斜め文字のリンクはアフィリエイトリンク
目次
ギャラリー
レビュー

1.概要
DP1シリーズは、デジタル一眼レフカメラのSD14 / SD15と同じ第2世代Foveonセンサーを搭載したコンパクトデジタルカメラで、無印:2008.3、s:2009.10、x:2010.9と約1年ごとにマイナーチェンジをおこなった。
記録画素数は450万画素 x3で実画素は450万画素で、JPEG記録とSIGMA PhotoProでは画素を合成してより高画素の出力もできる。
DP1とDP2の違いはレンズだけで、DP1が16.6mm、DP2が24.2mmのレンズを積んでいた。
画像処理チップはDP1、DP1sはTrue、DP1x、DP2、DP2s、DP2xはTrue IIを積んでいる。
DP1、DP2シリーズのバッテリー型番は、BP-31で3.7V 1300mAhの仕様となっている。
DP1シリーズは画像記録にX3Fしか対応していないため画像処理はSIGMA PHOTO PRO(以下、SPP)のみとなる。
DP1sの改良点
- ISO感度50の追加
- ISO感度設定で「オート」を選択した場合、「ISO AUTO」と表示
- ホワイトバランス設定で「オート」を選択した場合「AWB」と表示
- オートブラケットの表示箇所を画面左上に変更
- MFモード時に表示されるスケールにft(フィート)表示を追加
- グリッド表示に画面表示ボタンを押すと、液晶モニターが「アイコン表示」、「グリッド表示」、「アイコン非表示」、「液晶モニター表示」、「液晶モニターOFF」の順に切り替え
- 情報ソース:デジカメwatch 2009年10月2日記事
DP1xの改良点
- 「QS」(クイックセット)ボタンの搭載
- 画像処理エンジン「TRUE II」の搭載
- 「カラーモード」の搭載
- 「マイセッティング」の搭載
- ボタンレイアウトを「DP2」と統一
- AFE(Analog Front End)の搭載
- 情報ソース:デジカメwatch 2011年2月1日記事、ITmedia記事・2010年05月31日
・DP1シリーズ・背面ボタンの違い
- DP1とDP1sはボタン機能表示の印刷がすべて白色と一部ボタンは刻印のみでQSボタンがない。
- DP1xはすべてのボタンに機能表示が印刷され一部は赤色で印刷されている。
- 画像はシグマ配布資料から引用
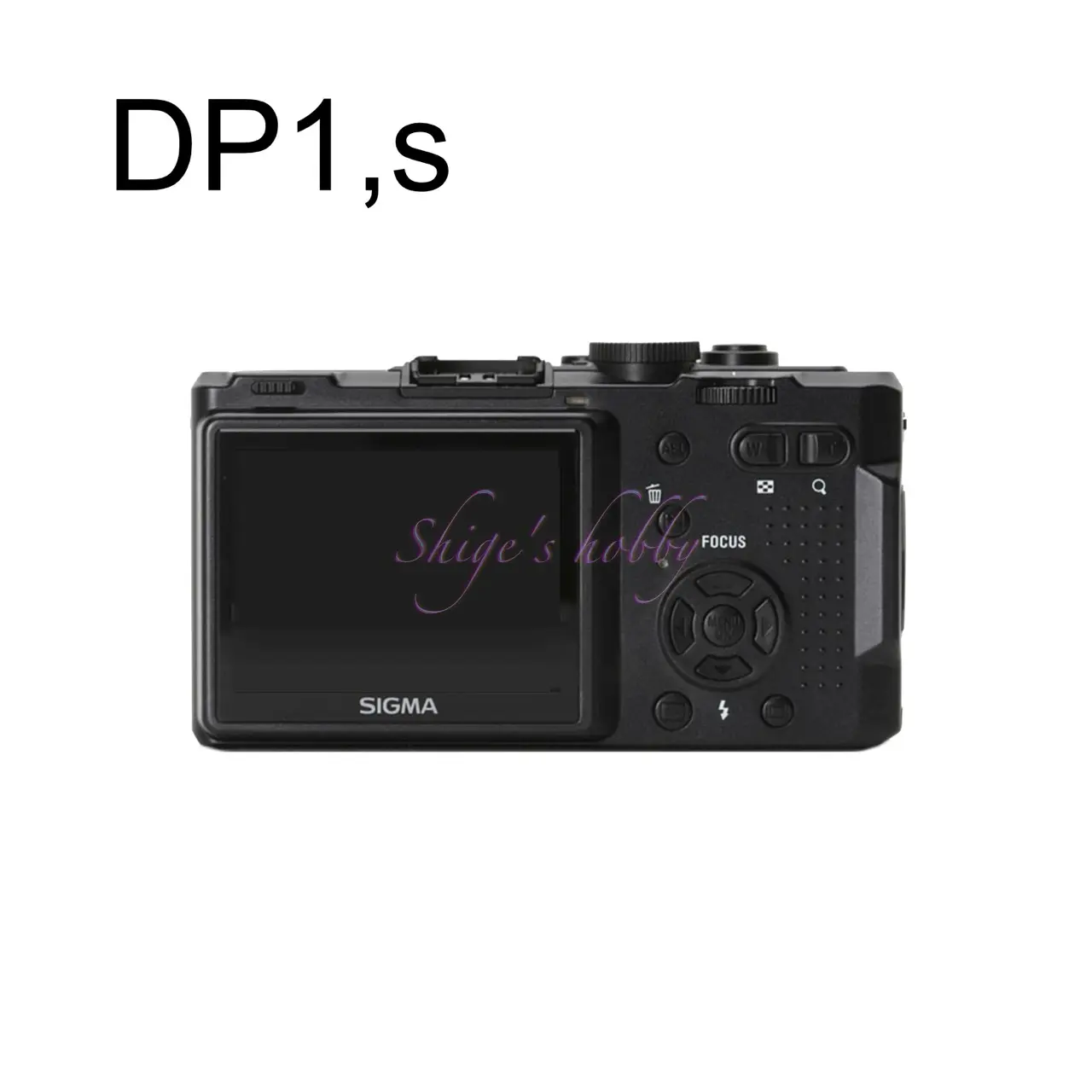

2.使用感
DP1シリーズは、Foveon特有のキレのある画像は、晴天下の光量のあるところで撮影した結果は今見ても十分に通用するけれど、このカメラを使っていた当時メインの被写体としていた猫にDP1を向けてみたが悲しい結果しか得ることができなかった。
通常、猫は素早く動き、暗いところを好むなど、DP1殺しのシチュエーションが多く、昼間の日向で寝ている猫くらいしか撮れなかった。
発売前はとても期待したカメラだった。しかし、無印DP1はとても動作が遅いカメラでカメラとして基本性能が初期のデジカメのようで使用には忍耐を要求された。
代表的な問題点としては、シャッターラグが大きい、液晶の追従性が悪い、オートホワイトバランスがいいかげん(Rawで撮れば後調整は可能)、バッテリーライフが短い、ISO感度を上げられない、手ぶれをしやすいなどがある。
こんなにコンパクトなカメラなのに、フィルム時代のRICOH GR1のようにカメラのコンパクトさを活かしてストリートスナップをするような用途には残念ながらまったく使えない代物だった。
よって、DP1は筆者にとっては落ち着いて風景をじっくり撮る用途でしか出番がなかった。しかし、それならば一眼レフを持ち出すほうがよい結果が得られるという矛盾を抱えることになる。
DP1、DP2シリーズはいずれの機種も電池持ちはよくなく、背面液晶のバッテリー表示が満タンでも電池電圧が足りなくなると突然死するという、SD9 / SD10と同じような症状を持っていた。
カメラの不良品も多く、時期によってはDP1を修理に出すとDP1xになって返ってくるという話も見聞きした。最初のDP1にせめてTrue IIを積んで、DP2シリーズとインターフェースを揃えた状態でリリースすれば、プロダクトの印象はそれほど悪くなかっただろう。
初代DP1はリリース時期を煮詰めることができないシグマのやらかした歴史の一つだ。デジタル一眼レフカメラのSD1でもリリース価格で煮詰めを誤った判断をして失敗していることも似たような事象だろう。
しかし、この時代にコンパクトデジカメのサイズにほぼAPS-Cセンサーを搭載したカメラをリリースしたことは素直に賞賛する。APS-Cクラスのセンサーを積んだカメラではライカX1が2009年、RICOHのGRが2013年発売であるため、2008年リリースの本カメラの先進性は際立っている。
筆者はDP1購入後にあきれて売り払った。その後DP1のマイナーバージョンアップ版DP1sはパスして、最終形のDP1xを入手した。Dp1xは画像処理チップがTrue IIになり、少しだけましなカメラになっていた。
しかし、DP1リリースから2年の時を経過してもそれほど使える代物にはならなかった。当時のシグマにはコンパクトデジタルカメラを成立させる基本的な要素技術が足りていなかったと思われる。
初代DPシリーズは発売から少したつとアウトレットのような形で中古市場に商品が流れ比較的安く買えた。2024年現在中古価格は上昇気味なのは動作個体が減っているからであろう。
現在はシグマにて修理受付もされていないので、壊れたらおしまいとなる。
カメラ本体の写真は、構図確認用にコシナ・ツァイスの25/28mmファインダーを載せている。外付けファインダーはシグマからの純正のビューファインダー、VF-11が販売されている。
外付けファインダーは構図を確認するだけでピント位置などカメラ側の情報は表示されない。
以前は純正バッテリー終売後に互換バッテリーを売っているのを見かけているけれど、最近は互換バッテリーも市場から無くなっている(アマゾンに怪しげな互換品があるが怖いので紹介はしない)ため、中古のボディを手に入れた方はバッテリーの入手に苦労しそうな気がするので注意していただきたい。
3.まとめ
結論としてDP1シリーズをまとめると、リリースの発表があったとき、大サイズセンサーに28mm相当のレンズを積んだデジカメ、しかもFOVEONと言うことで、RICOH GR1の再来をものすごく期待した。そして、DP1を発売日に入手して見事に期待は裏切られた。
DP1には3機種あるけれど、画像処理チップが古い世代のTrueを搭載した無印DP1とDP1sはかなり危険、True IIを積んだDP1xで多少マシになるけれどマシというレベルだ。
いずれにしろ、DP1シリーズを使うならば、手ぶれのリスクと撮影テンポに相当の忍耐を要求されること覚悟して使う必要がある。
また、発売から15年以上経過しているため、センサーを含む電子基板の劣化による故障も懸念される。
2025年現在、オールドデジカメブームのようなあやふやなブームにのって、DP1シリーズもびっくりするような中古価格で流通しているのをみかける。しかし、所詮は450万画素のコンデジなので、1万円程度ならまだしも、数万円の価格を出してまで使うカメラではない。同じセンサーを楽しむのであればSD14かSD15のほうが安定した撮影が楽しめる。
・X3Fファイル
X3Fファイルは、R,G,Bの3色の情報を1ピクセル毎に保存しているため、通常のベイヤーセンサーの3倍のデータ量となる。
このX3Fを処理するSIGMA PHOTO PRO(以下、SPP)はSD9のころから使用している。リリース当初は動作が不安定、動作が遅いと文句を言っていた。
しかし、2024年のM2 Pro搭載のMac miniで使用したところ、SPPの不用意なクラッシュはほとんど見られず、画像の処理速度も実用に十分な速度に達していることが実感できた。PCのCPUパワー増大による処理速度向上の恩恵を感じる出来事だ。
フリーウェアのX3FをDNGに変換するユーティリティソフトも使用したことがあるけれど、使用した時期のバージョンはDNGに変換した後の画像から、かなり画像処理しないとSPPと同じクオリティにすることは困難で、その手間をかける必然性を見いだせなかった。その後、ソフトウェアが改良されているかは不明だ。
DNG変換後の画像がSPPデフォルトと同等の画像を得ることができれば、他のソフトで微調整をするのが他のソフトウェアを使い慣れたユーザーには理想的な作業フローと考えたがそうはならなかった。
変換ソフトは個人が作成したフリーウェアなので、利用者が文句を言う筋合いが無いことも確かだ。
画像処理ソフトのAffinity Photoで現像ができることがわかったので、こちらのページでテストしてみた。こちらもSPPと同じ結果を得るためには、入念に調整方法を研究しなくてはいけないことはわかっている。
しかし、APPLEのM-CPUにSPPが対応したおかげで、ストレス無く調整した画像を出力できるようになったため、あまり深追いはしていない。SPPで出力したJPGをAffinity Photoで最終調整するのが今のところベターな作業フローだと考えている。
2024年現在、新規Foveonセンサーの開発は滞っているようである。今後、新しいX3Fデータに巡り会うことがあるのか、興味深く待っている。
仕様・シリーズカメラ比較
| 項目 | DP1 | DP1s | DP1x |
| カメラ有効画素数 | 有効画素:約1,406万画素 (2,652×1,768×3層) | 有効画素:約1,406万画素 (2,652×1,768×3層) | 有効画素:約1,406万画素 (2,652×1,768×3層) |
| 焦点距離 | 16.6mm F4 (35mmカメラ換算:28mm相当の画角) | 16.6mm F4 (35mmカメラ換算:28mm相当の画角) | 16.6mm F4 (35mmカメラ換算:28mm相当の画角) |
| レンズ構成 | 5群6枚 | 5群6枚 | 5群6枚 |
| 最大絞り | 4 | 4 | 4 |
| 最小絞り | 11 | 11 | 11 |
| 絞り羽根 | 6 | 6 | 6 |
| 撮像素子 | FOVEON X3®(CMOS)・20.7×13.8mm | FOVEON X3®(CMOS)・20.7×13.8mm | FOVEON X3®(CMOS)・20.7×13.8mm |
| 画像処理 | TRUE | TRUE | True II |
| 背面液晶 | 2.5型・23万ドット | 2.5型・23万ドット | 2.5型・23万ドット |
| ファインダー | 光学式 ビューファインダー VF-11 | 光学式 ビューファインダー VF-11 | 光学式 ビューファインダー VF-11 |
| 最短撮影距離(m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー(BP-31) | リチウムイオンバッテリー(BP-31) | リチウムイオンバッテリー(BP-31) |
| 記録メディア | SD メモリーカード SDHC メモリーカード マルチメディアカード | SD メモリーカード SDHC メモリーカード マルチメディアカード | SD メモリーカード SDHC メモリーカード マルチメディアカード |
| 外形寸法(mm) | 幅 x 高さ x 奥行 113.3mm × 59.5mm × 50.3mm | 幅 x 高さ x 奥行 113.3mm × 59.5mm × 50.3mm | 幅 x 高さ x 奥行 113.3mm × 59.5mm × 50.3mm |
| 重量(g) | 約250g (電池、メモリーカード除く) | 約250g (電池、メモリーカード除く) | 約250g (電池、メモリーカード除く) |
| リリース年 | 2008年3月3日 | 2009年10月10日 | 2010年9月30日 |
| 価格 | 10万円(Open) | 54,800(Open) | 72,800(Open) |
オプション
参考情報
広告
- シグマ DP 中古・Ads by Rakuten
- シグマ SD 中古・Ads by Rakuten
- シグマ SD 中古・Ads by Rakuten
- シグマ・Ads by Amazon
- シグマレンズ・Ads by Amazon
- シグマ書籍・Ads by Amazon
- シグマ SD14・Ads by Amazon
- シグマ SD15・Ads by Amazon
- シグマ SD1・Ads by Amazon
- SIGMA BP-21・Ads by Amazon
- SIGMA レンズフード LH1-01・Ads by Amazon
- フード:HA-11 (DP1,DP1s,Dp1x向け)・Ads by Amazon
- ファインダー:VF-11(DP1シリーズ向け 28mm相当)・Ads by Amazon
- dp0 Quattro・Ads by Amazon
- sd Quattro H・Ads by Amazon

更新履歴
- 2025.4.13
- 2024.8.17
- 2024.06.26:改稿
- 2024.03.27:改稿
- 2023.01.01:初稿



Be First to Comment